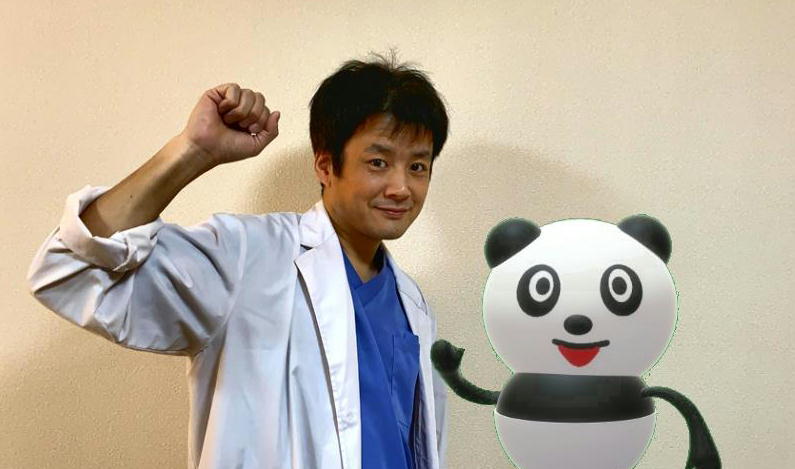 ブログつれづれ養生訓
ブログつれづれ養生訓 令和6年度イベント、講座案内
令和6年度イベント、講座案内 令和6年度イベント、講座案内 中国医学が活性化しています。色んなイベント・講座のご案内です。 3月20日 脈診デバイス、舌診アプリ完成内覧会 大阪中央公会堂 小集会室 4月 薬膳講座開催します~薬膳ごはん術~ ...
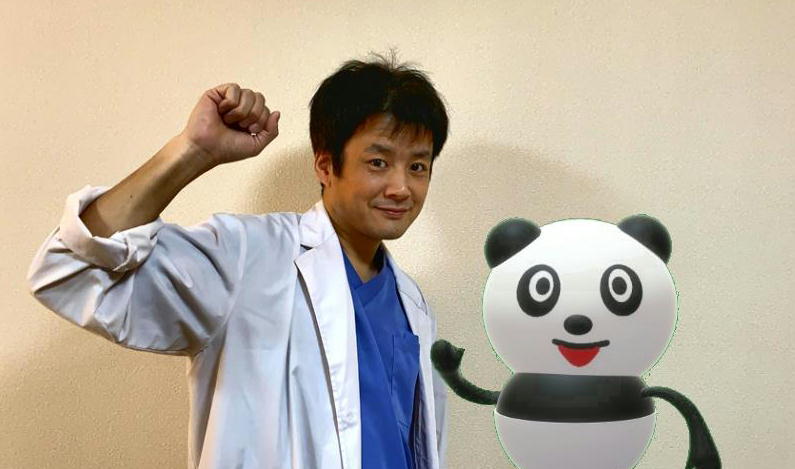 ブログつれづれ養生訓
ブログつれづれ養生訓  立ちくらみ
立ちくらみ  めまい
めまい  貧血
貧血  ブログつれづれ養生訓
ブログつれづれ養生訓 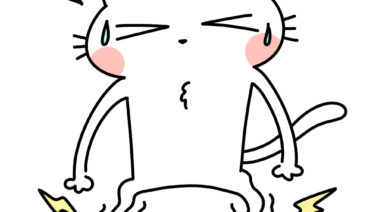 こむら返り
こむら返り  めまい
めまい  めまい
めまい  吐き気
吐き気  めまい
めまい