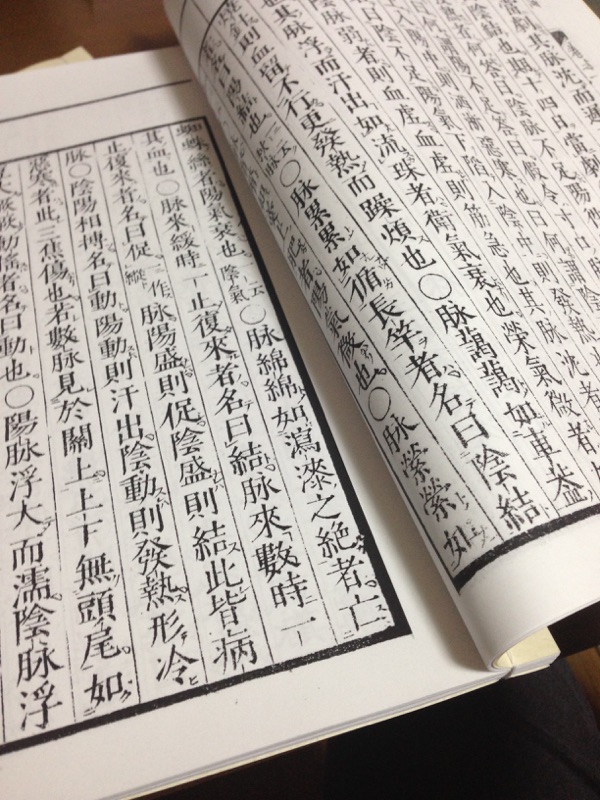 ブログつれづれ養生訓
ブログつれづれ養生訓 令和6年9月中国医学講座開講!生徒募集中♪
令和6年9月中国医学講座開講!生徒募集中♪ 中国医学が注目されています。 皆さん勉強しませんか? 漢方薬を処方する方、色んなテキスト読んで勉強されていると思いますが、もやっとしませんか?患者さんの状態にピタッと当てはまらない。表現が曖昧すぎ...
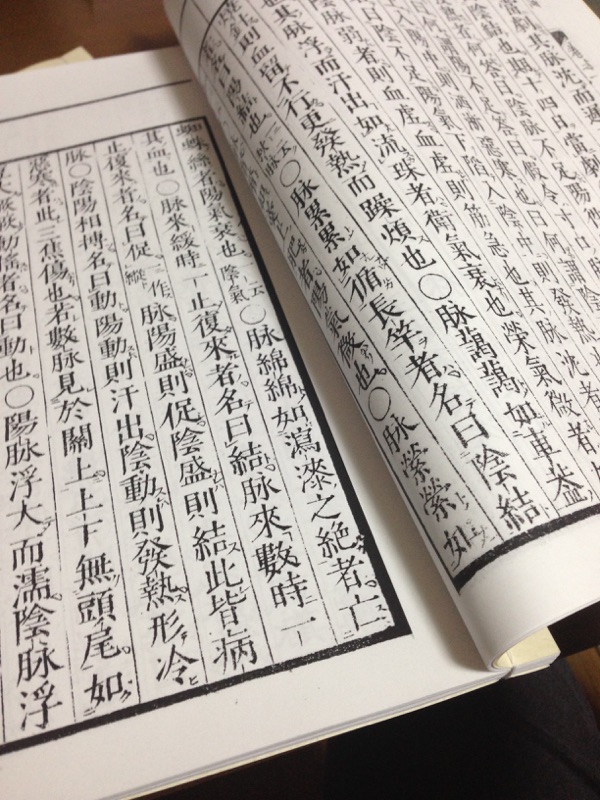 ブログつれづれ養生訓
ブログつれづれ養生訓  ブログつれづれ養生訓
ブログつれづれ養生訓  ブログつれづれ養生訓
ブログつれづれ養生訓 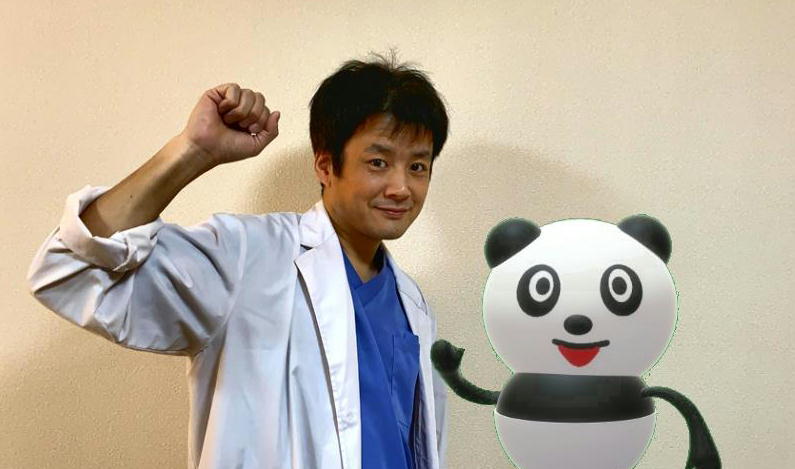 ブログつれづれ養生訓
ブログつれづれ養生訓  ブログつれづれ養生訓
ブログつれづれ養生訓 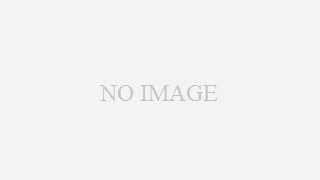 ブログつれづれ養生訓
ブログつれづれ養生訓  歯痛
歯痛  乾燥肌
乾燥肌  ブログつれづれ養生訓
ブログつれづれ養生訓  ガス、腸鳴
ガス、腸鳴