 PMS
PMS ストレスから食べてしまう人を正当化してみる
ストレスから食べてしまう人を正当化してみる フーフーです。ちょっとしたことあるとやられちゃいます。メンタル弱いです。さらにそのストレスで食べすぎて…。意思も弱いです。 はい、食べちゃうんですね。 でもそんな方多いですよね。依存症的になってい...
 PMS
PMS 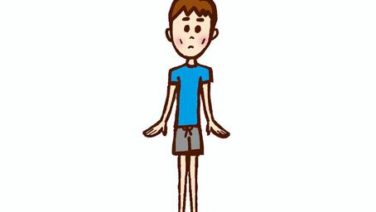 下痢
下痢  多汗
多汗  イライラ
イライラ  吐き気
吐き気  食物アレルギー
食物アレルギー  下痢
下痢 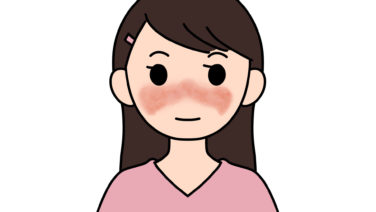 免疫系疾患
免疫系疾患  生理不順
生理不順  いびき
いびき