 吐き気
吐き気 気象病ってどんなの?
気象病ってどんなの? フーフーです。 気象病ってどんなの? 雨が降ると頭が痛くなる? 気象病とは、気候や天気の変化によって、体の不調が引き起こされる状態の総称です。 頭痛やめまい、倦怠感や節々の痛み、時には吐き気や喘息、などの内科系疾患も引...
 吐き気
吐き気  めまい
めまい  蕁麻疹
蕁麻疹  パニック障害
パニック障害  下痢
下痢  ブログつれづれ養生訓
ブログつれづれ養生訓  冷え性
冷え性 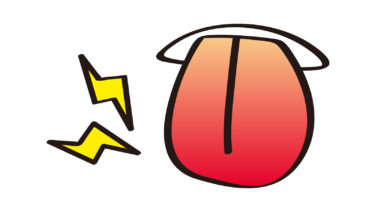 頭痛
頭痛  呼吸器系
呼吸器系 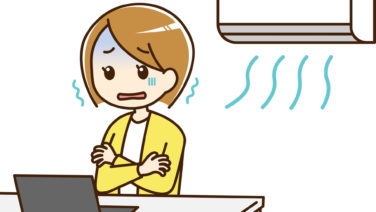 頭痛
頭痛