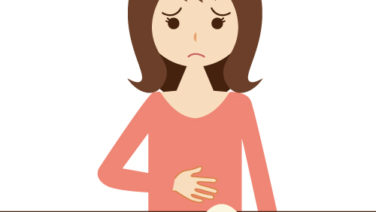摂食障害を考える
摂食障害を考える
フーフーです。摂食障害の相談が来ました。なんで起きるんですか。
摂食障害は、食事を食べられない、または自分ではコントロールできずに食べ過ぎる、他には、いったん飲み込んだ食べ物を吐いてしまうなど、患者さんによっていろんな症状がありますよね。
心の疾患、肝、腎、肺も原因になることはありますが、胃と脾臓、それと湿証が加わって起きることが多いです。イメージで言うと胃の出口の幽門のところ、十二指腸のあたりに飲と言われる水分が溜まったり、むくみが発生していると起きやすいです。
出口が詰まってるために食べ物が降りない、消化のために胃熱が発生している。下に降りないから吐きたいと言う状態になります。吐瀉物が冷たいか、熱いかによっても薬の処方は変わります。
そして、胃の出口に湿が溜まると言うことは、体の内部にも溜まり、下半身が浮腫む、足も浮腫むなども起きやすいです。
そのため、不安が生まれたり、子宮や卵巣の機能低下、性欲減退などがメンタル面に発生します。思考の低下、被害妄想などもありますね。
体の方にも疾患は現れて、体重の増減、水様便、冷えや、倦怠感。起きれない、アレルギー疾患なども出やすいです。
対策としては、舌をみて、歯形や、舌のむくみが無くなるまで、水分を減らすこと。
利尿できるようにマッサージや発汗、ウォーキング等の運動を特に下半身中心に行うのが良いかと思います。
2023.02.12
ガス、腸鳴パニック障害震え急性胃炎鬱吐き気生理不順摂食障害ブログつれづれ養生訓便秘胃下垂胃もたれ
 ガス、腸鳴
ガス、腸鳴