 倦怠感
倦怠感 夏は十割蕎麦がおすすめ
夏は十割蕎麦がおすすめ フーフーです。 夏は暑い!暑いと冷たいお蕎麦が食べたいです。どうでしょう。 夏の盛りそばやざるそば!いいですね。 美味しいです。 特にこのそばの作用もいいと思います。 そばの効能はズバリ、利水作用と健脾作用です。 胃...
 倦怠感
倦怠感 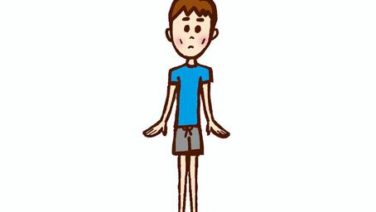 生理不順
生理不順  ガス、腸鳴
ガス、腸鳴 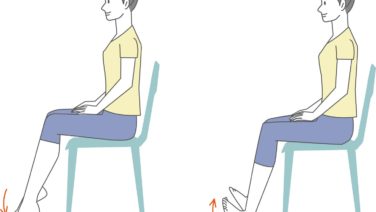 便秘
便秘  鬱
鬱  ガス、腸鳴
ガス、腸鳴 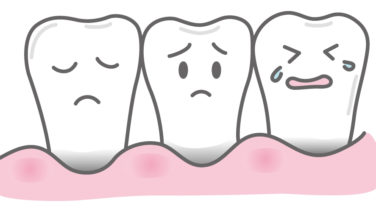 歯痛
歯痛 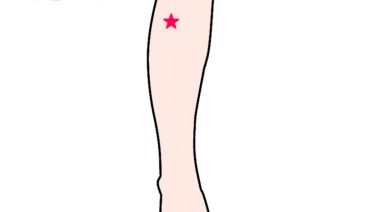 急性胃炎
急性胃炎  ブログつれづれ養生訓
ブログつれづれ養生訓  胃下垂
胃下垂