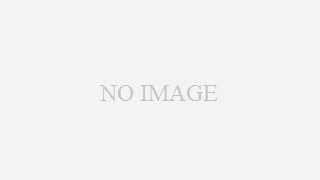 ブログつれづれ養生訓
ブログつれづれ養生訓 地域の特性と健康
地域の特性と健康 フーフーです。 住む地域の体に与える影響を教えてください。 いろいろあるでしょうね。 北と南も違いがありますし、山陽、山陰も違います。 海沿い、山沿いも違います。 さらにそこで採れる農作物も体に影響を与えます。 本当にいろ...
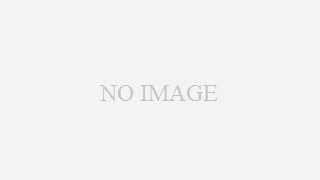 ブログつれづれ養生訓
ブログつれづれ養生訓  突発性難聴
突発性難聴 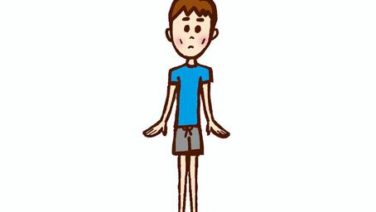 下痢
下痢  ブログつれづれ養生訓
ブログつれづれ養生訓  頭痛
頭痛  ブログつれづれ養生訓
ブログつれづれ養生訓  パニック障害
パニック障害  ブログつれづれ養生訓
ブログつれづれ養生訓  外反母趾
外反母趾 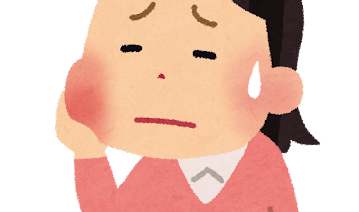 ブログつれづれ養生訓
ブログつれづれ養生訓