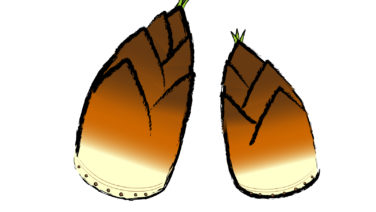 下肢静脈瘤
下肢静脈瘤 さて、とりあえずタケノコを食べとこう
さて、とりあえずタケノコを食べとこう フーフーです。 タケノコをいただきました。効能を教えてください。 この時期のタケノコは良いですね。 ズバリ利尿効果。 特に今の時期に食べるのがおすすめです。 だんだん暖かくなり、むしろ暑くなってくる今。...
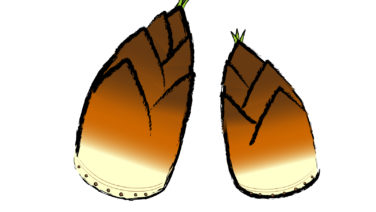 下肢静脈瘤
下肢静脈瘤  痺れ
痺れ  橋本病
橋本病  橋本病
橋本病  下痢
下痢  下痢
下痢  橋本病
橋本病  食物アレルギー
食物アレルギー  味覚障害
味覚障害 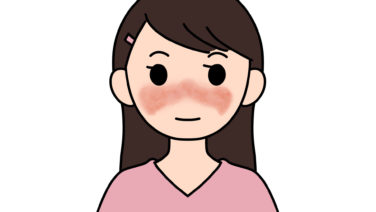 膠原病
膠原病