 動物アレルギー
動物アレルギー 昭和風健康法~体質改善海水浴
フーフーです。 子供の時、よく海水浴に行きました。 身体には良いの? 海水浴は現代病にいいかと思います。 ミネラルたっぷりの海水によって、汗をかきやすいデトックス体質の皮膚に生まれわかります。さらに太陽に光によってその効果がアップ。 アトピ...
 動物アレルギー
動物アレルギー 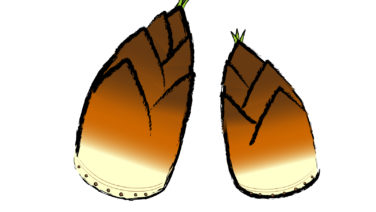 橋本病
橋本病  橋本病
橋本病  消化器疾患
消化器疾患  吐き気
吐き気  ブログつれづれ養生訓
ブログつれづれ養生訓  痒み
痒み  橋本病
橋本病 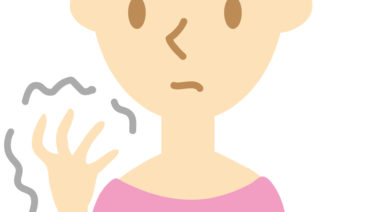 めまい
めまい  無呼吸症候群
無呼吸症候群