あったかくなってきたのに起きる冷え性
あったかくなってきたのに起きる冷え性
フーフーです。冷え性は冬だけじゃないみたいですね。今の時期も冷え性あります。なんで?
中医学では、季節に関係なく、非常に冷え性のある人や手足が冷たくなる人ありますね。このような症状は、腎、脾、肺の虚弱によって引き起こされる可能性があります。これらの臓器は、体内の物質を動かす役割を果たしており、非常に重要な役割を担っています。
まず、腎は体内の水分調整に関与しています。腎弱くなると、体内の水分が余分にたまり、浮腫を引き起こす可能性があります。浮腫は、足や手、腰がむくみます。これによって、血流が悪くなり、手足が冷えたり低体温になったりすることがあります。
また、脾は食べ物から栄養素を吸収し、体に必要なエネルギーを生み出します。もし脾が弱くなると、消化能力が低下し、栄養素や気が不十分になり、手足の冷えや低体温を引き起こす可能性があります。気虚っていいます。さらに、脾は水分を制御することもできます。昇清作用と言って水分を上にあげるんですが、これが弱くなります。すると浮腫がおき、手足の冷えや低体温が発生する可能性があります。
最後に、肺は体の気を制御するために必要な臓器です。肺が弱くなると、呼吸が浅くなり、体が十分に酸素を得られなくなります。これによって、手足が冷えたり低体温になったりすることがあります。
そこで、手足の冷えや低体温を改善するためには、腎、脾、肺の機能を強化することが重要です。これには、食事の改善、漢方薬、鍼灸、マッサージなどが効果的です。一言で言うと血行良くして下さいです。あと足元冷やさないでくださいね。
2023.05.10
いびき無呼吸症候群めまいブログつれづれ養生訓肩こり・痛み・痺れ・だるさ
 爪
爪  爪
爪 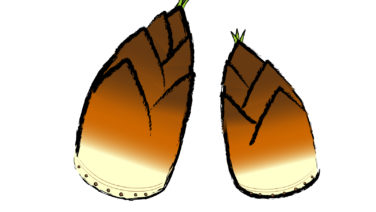 下肢静脈瘤
下肢静脈瘤  顔面麻痺
顔面麻痺  顔面麻痺
顔面麻痺  頭痛
頭痛  いびき
いびき  乾燥肌
乾燥肌 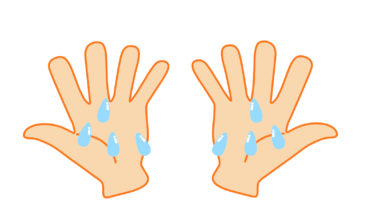 手汗
手汗  こむら返り
こむら返り