 ブログつれづれ養生訓
ブログつれづれ養生訓 中国医学の診断のすすめ
中国医学の診断のすすめ フーフーです。 中国医学の勉強したいという方が増えてきたように思います。 おすすめポイントをさらにまとめてください。 中国医学のポイントは、ズバリ診断力です。 体質診断。先日、発表しました舌診アプリ。 舌の写真を撮る...
 ブログつれづれ養生訓
ブログつれづれ養生訓 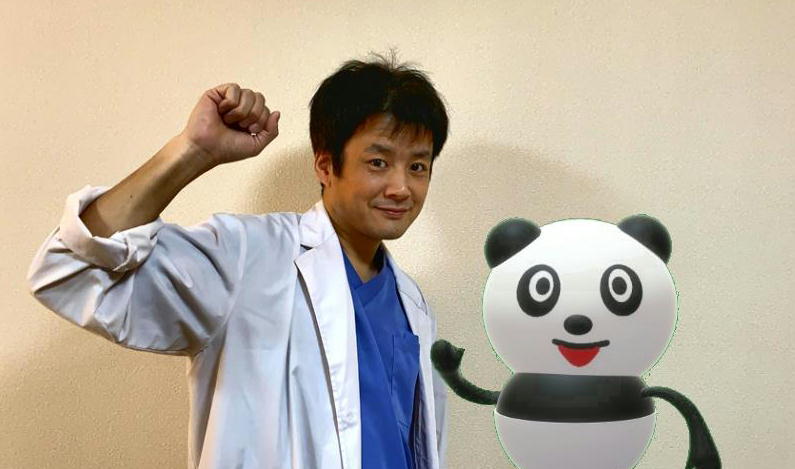 ブログつれづれ養生訓
ブログつれづれ養生訓  ブログつれづれ養生訓
ブログつれづれ養生訓  ブログつれづれ養生訓
ブログつれづれ養生訓  ブログつれづれ養生訓
ブログつれづれ養生訓  頭痛
頭痛  ブログつれづれ養生訓
ブログつれづれ養生訓 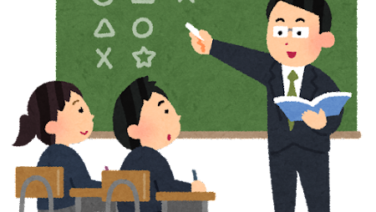 ブログつれづれ養生訓
ブログつれづれ養生訓  ブログつれづれ養生訓
ブログつれづれ養生訓  消化器疾患
消化器疾患