 骨粗鬆症
骨粗鬆症 鯛の効能は
鯛の効能は フーフーです。 この前食べた鯛が美味しかったです。 効能はなんですか。 鯛良いですね。 脾胃の働きを強くすること。それと骨を強化してくれることこれがかなり強いですね。 あとは、体力増強も期待出来ます。 なんせ明石の早い海流や、鳴...
 骨粗鬆症
骨粗鬆症  冷え性
冷え性  ブログつれづれ養生訓
ブログつれづれ養生訓 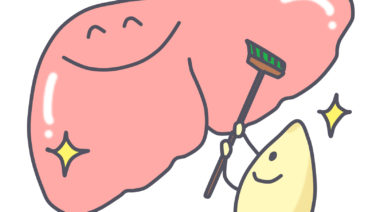 四十肩
四十肩  鬱
鬱  ガス、腸鳴
ガス、腸鳴  こむら返り
こむら返り  いびき
いびき 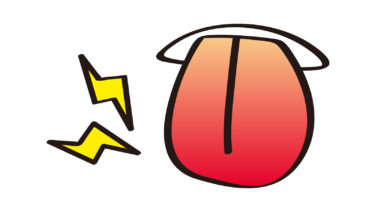 甲状腺機能亢進
甲状腺機能亢進 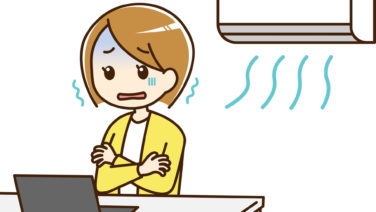 頭痛
頭痛